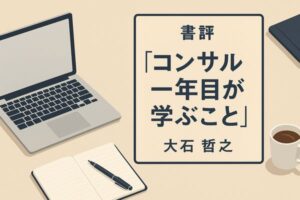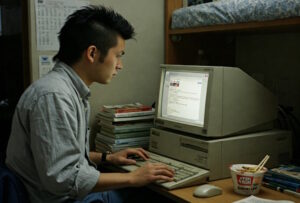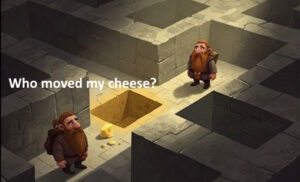- 書名: 失敗の科学 失敗から学習する組織、学習できない組織
- 原題: Black Box Thinking: The Surprising Truth About Success
- 著者: マシュー・サイド
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン(2016年12月発売/原書2015年)
- Audible聴き放題対象作品 【Audibleの無料体験で聴く】
はじめに
本書は前書きもなく、静かに一つの家庭の朝から始まる。登場するのは、良き父であり、良き夫であり、そして航空パイロットでもあるマーティン・ブロミリー。だが、タイトルが示す通り、この物語は「悲劇」へと向かっていく。
2005年3月29日、父マーティン・ブロミリーは6時15分に目を覚ますと、子ども部屋に向かった。幼い娘のビクトリアと息子のアダムに身支度をさせるためだ。支度を済ませた子どもたちは朝食をとろうと元気いっぱいに階段を駆け下りていった。数分後、ベッドで少しゆっくりしていた母親のエレインも食卓に加わった。
それが、彼女にとって最後の家族団らんの朝となった。
エレイン・ブロミリー(当時37歳)は副鼻腔炎の手術を受ける予定だった。執刀医も麻酔科医も経験豊富なベテランだ。手術自体は「ありふれたもの」。医師たちにとってもルーチン業務の一つだった。
しかし、麻酔導入後に気管挿管がうまくいかず、エレインの酸素飽和度はみるみる低下していく。選択肢がなかったわけではない。看護師が気管切開の準備を整え、声もかけた。それでも医師たちは、その提案に一瞬振り返っただけで、ひたすら挿管に固執し続けた。

結果として、エレインは手術室で重篤な低酸素性脳障害を負い、そのまま意識が戻ることはなかった。息を引き取ったのは、昏睡状態に陥ってから13日後のことだった。
この悲劇をきっかけに、マーティン・ブロミリーは「なぜあの事故は起きたのか」「なぜ止められなかったのか」を問い続け、自らの航空パイロットとしての経験で培った「人間的要因」の視点から、医療安全の改革に深く関わるようになる。
彼の証言動画「Just a Routine Operation」は、医療現場で何が起きうるのかを示すものとして、いまなお多くの医療従事者に視聴され続けている。
大事な点は、この事故が「誰かの無能」では説明できないということだ。ベテラン医師が揃い、看護師の判断も的確だった。それでも最悪の事態が起きたのは、医療現場特有の強い階層構造や、緊急時におけるプレッシャー、あるいは「失敗は許されない」という文化の中で、「異なる意見や声」が、経験や権威の前にかき消されてしまったことにある。著者マシュー・サイドは、その構造的な問題に光を当てていく。
sec.1 成功を分けるのは「失敗との付き合い方」
この本が描いているのは、失敗から学べる組織と、学べない組織の分かれ道である。
そして、その最も劇的な例として、人命を預かる二つの現場、航空業界と医療業界を対比させる。いずれも高い専門性と即時的な判断が求められる職場であり、失敗が死につながるという点では共通している。しかし、その「失敗への向き合い方」には決定的な違いがある。
たとえば、航空業界におけるジェット機の事故発生率は、欧米の統計によると100万フライトあたりわずか0.41件。これは、単純計算で約240万回飛んで1回事故が起きるレベルである。一方、医療業界ではアメリカの推計によれば、年間5万人から最大40万人が、回避可能な医療ミスで命を落としている。これは「心疾患」「がん」に次ぐ第三の死因とすら言われている。
なぜこれほどまでに航空業界の安全性が高まったのか? そして、なぜ医療業界ではいまだに同様の進歩が見られないのか?
マシュー・サイドは、その違いを「組織文化」に求める。失敗をチーム内で放置し、隠蔽したままにするクローズドループ型の組織か、あるいは逆に、失敗を公開し学びに変えるオープンループ型の組織か。この違いが、組織の未来と人々の運命を大きく分けるのだ。
航空業界はなぜ「失敗から学べる」のか
もちろん、航空業界も最初からミスの少ない業界だったわけではない。
1912年のアメリカ陸軍では、14人のパイロットのうち8人が事故で命を落としていた。航空学校における訓練中の死亡率も25%に達していたと記録されている。つまり、かつての空は、医療現場以上に「死」が日常だった。
航空安全対策の転機となったのが、1978年のユナイテッド航空173便事故だ。
着陸直前、ランディングギアの表示異常に気を取られた機長は、燃料残量の深刻さに意識が向かず、気が回らないまま時間を費やしてしまった。副操縦士や機関士は何度か燃料の状況に触れたが、機長が耳を傾けるまで強く警告するには至らなかった。そこには、階層的な権威関係が影を落としていた。
この構図は、まさにエレイン・ブロミリーの手術室と同じだ。
看護師は気管切開の必要を感じ、準備もしていた。しかし、医師たちは口頭挿管に固執し、最終的には看護師の声がかき消された。
医師や機長の視野狭窄、チーム内の沈黙、経験への過信――事故の構造は驚くほど似ていた。有無を言わせぬ上下関係が、チームワークを崩壊させた点も共通している。
だが、決定的な違いは、事故の「後」である。
航空業界は、173便事故をきっかけにCRM(クルー・リソース・マネジメント)を導入し、組織の力学そのものを再設計した。すなわち、チーム内のコミュニケーションを改善し、立場に関係なく誰もが安全に関わる懸念を発言できるようトレーニングを始めたのだ。
さらに、航空業界では、ミスや事故が発生すると、強い権限を持つ独立の調査機関によって即座に記録・分析される。
個人を責めるのではなく、「なぜそれが起きたのか」を組織全体で共有し、再発防止のための対策が講じられる。この仕組みが「オープンループ」だ。
この文化が、失敗を責任追及ではなく“進化の素材”として扱う文化を生み出している。その結果として、今日のような極めて低い事故率が実現している。
医療業界はなぜ「失敗から学べない」のか
一方、医療業界は、まったく逆の構造に陥っている。
患者の死亡や重篤な合併症が起きても、それが組織的に共有され、改善に生かされることは少ない。ミスは個人の責任にされ、あるいは隠ぺいされ、恥とみなされる傾向がある。これが「クローズドループ」だ。
最近も、NHK『クローズアップ現代』で、ある脳外科医が関与した医療事故の事例が報じられた。報道を通して見えてくるのは、失敗の原因やプロセスが明るみに出る構造が、日本の医療現場においてはまだまだ未整備であるという事実だ。
参照:
マシュー・サイドはこの構造を、医療過誤の統計で裏付けている。アメリカでは、年間5万人から40万人が、回避可能な医療ミスによって命を落としている。これは「心疾患」「がん」に次ぐ、第三の死因だとも言われている。
著者は、ある医師の言葉を引用する。
「これは、ボーイング747が毎日2機墜落しているようなものです。あるいは、2ヶ月に1回『9.11』が起きているようなものだ。」
それほどの規模で“事故”が起きているのに、世間の認識は驚くほど鈍い。なぜか?
それは、まさに情報が、クローズドループの中で閉ざされているからだ。失敗が表に出ず、共有されないため、個人も組織も、そして社会全体もそこから学ぶ機会を逸してしまうのである。
なぜ学べないのか?──「システム」と「マインドセット」
著者は、失敗から学ぶためには、2つの条件が必要だと言う。それは単に個人のスキルや注意力の問題ではなく、より根本的な要素である。
- システム:失敗を記録し、共有し、改善へとつなげるための、仕組みやプロセス。航空業界の事故調査機関やCRMなどがこれにあたる。
- マインドセット:「失敗は恥ずべきこと」「あってはならないこと」という固い観念を乗り越え、失敗を学びの機会として捉える意識。
医療の現場では、優秀な医師ほど、自らのミスを「不運な出来事」「個人の能力の限界」だと片付けたり、あるいは認めること自体に強い抵抗を感じる傾向がある。これは、極めて高い専門性と人命を預かる責任ゆえに、「完璧」であろうとする意識や、ミスを認めるとキャリアや評判を失うリスクがあるといった要因が絡み合っている。こうしたマインドセットは、組織としての学習を妨げる最大の要因となる。
一方、航空業界では、個人の失敗やヒヤリハットは、システムによって速やかに全体の資産となる。この「システム」と「マインドセット」の両輪が機能するかどうかが、組織進化のスピードと、そこで働く人々の安全性、そして顧客(患者)の運命を大きく分けるのだ。
あなたの属する組織は、失敗を隠す「クローズドループ」に陥っていないだろうか? それとも、失敗を次の成功のための糧とする「オープンループ」として機能しているだろうか? 本書は、その問いを私たち一人ひとりに、そして社会全体に投げかけている。
まとめ
本書は、第一章で提示した航空と医療の鮮やかな対比を出発点とし、司法、教育、スポーツ、ビジネスといった多様な分野の事例を縦横無尽に駆け巡りながら、失敗から学ぶための視点と方法を提示していく。
その核心にあるのが、本書の原題である『Black Box Thinking』だ。
これは、航空機の事故原因を究明するブラックボックスのように、失敗という避けがたい現実から目を背けず、そこに記録された事実(何が起きたのか、なぜ起きたのか)を徹底的かつ客観的に分析し、次の成功や安全に結びつけようとする思考様式、あるいは組織文化である。
個人の「失敗したくない」という自然な心理や、組織の体面が学習を妨げる「クローズドループ」に陥る多くの事例がある中で、この「ブラックボックス思考」、すなわち失敗を隠さず、学びの糧とする「オープンループ」の姿勢こそが、持続的な改善と進化を可能にするのだ。
「失敗はコスト」ではなく「失敗はデータ」であるという認識の転換こそが、個人と社会を前進させる。本書は、失敗を科学することを通じて、社会は今よりきっと良くなる、そんな希望を私たちに抱かせてくれる一冊だ。
\ 書評本はAudibleで聴いています/