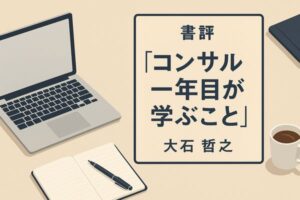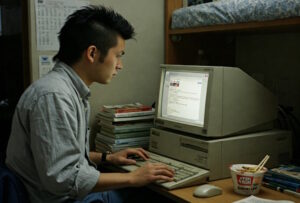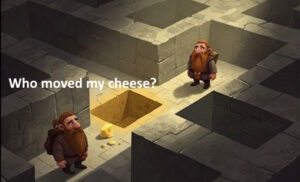- 書名: 1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術
- 著者: 伊藤 羊一
- 出版社: SBクリエイティブ
- 発売日: 2018.3.14
- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】
- 目次:
- 序章 そもそも「伝える」ために考えておくべきこと
- 第1章 「伝える」ための基本事項
- 第2章 1分で伝える―左脳が理解するロジックを作る
- 第3章 相手を迷子にさせないために「スッキリ・カンタン」でいこう
- 第4章 1分でその気になってもらう―右脳を刺激してイメージを想像させよう
- 第5章 1分で動いてもらう
- 第6章 「伝え方」のパターンを知っておこう
- 第7章 実践編
はじめに
伊藤羊一の著書『1分で話せ』は、単に「話し方」の技術を教えるのではなく、聞き手を「動かす」ための「伝える技術」に焦点を当てた一冊だ。ヤフーアカデミア学長やソフトバンクアカデミアでの実績を持つ著者が、孫正義氏にも注目された自身のプレゼン経験に基づいてその骨子を解説している。本書は、日々のプレゼンや報告、商談など、あらゆるビジネスシーンで自分の意見を効果的に伝え、相手に行動を促すためのノウハウを紹介している。
以前に、コンサル会社出身の大石哲之氏の著作『コンサル一年目が学ぶこと』を書評したが、プレゼンの方法論としては、本書との共通点も多かった。
ただし、大石氏の著書が思考法から資料作成まで幅広くカバーするのに対し、この本は「話して相手を動かす」ことだけに絞り込んでいる。大石氏が「正しく考える」ことを重視するなら、伊藤氏は「とにかく相手を動かす」ことを最優先にしている。
この違いには、著者の会社員としての経験が大きく影響している。「根回しもアフターフォローもプレゼンの一部」と考えたり、「1分で話せないなら何時間話しても無駄」と割り切ったりする発想は、現場で揉まれた人ならではだ。話術に特化したからこそ、すぐに使える具体的なテクニックを深く掘り下げることができている。以下に、本書の具体的な内容を整理してみよう。
【要約】一分で話せ
プレゼンの本質を理解する
この本は厳しい現実から始まる。人は相手の話の80%は聞いていない、あるいは理解していない。どんなに完璧なプレゼンをしても、自分の考えが100%伝わることはない。著者は経験から「1分でまとまらない話は、何時間かけても伝わらない」と断言する。逆に言えば、どんな話でも1分で伝えられるのだ。
プレゼンの真の目的は、「理解してもらう」ことでも「きれいに話す」ことでもない。聞き手を「動かす」ことだ。そのためには「誰に、何を、どうしてもらいたいのか」を具体的に決める必要がある。
「誰に」伝えるかを考える際には、相手の立場、興味、プレゼンに何を求めているか、専門知識の理解度、どのような言い方をすればネガティブな反応をするか、といった要素を具体的にイメージすることが重要だ。最終的なゴールは、聞き手がどのような状態になるか、具体的な行動まで設定すること(例:上司に、営業部の○○さんにかけあってもらう)が求められる。
さらに、プレゼンは当日の発表だけで完結するものではない。相手を動かすためには、プレゼン前の「根回し」や席配置の工夫、そしてプレゼン後の「アフターフォロー」まで、できることはすべてやる必要がある。
左脳に訴える論理構造
1分で伝えるためには、聞き手の左脳(ロジック)と右脳(感情)の両方に働きかける必要がある。まず左脳を納得させるロジックから見ていこう。
話は「結論」を最初に述べ、その後に「3つ程度の根拠」を示す「ピラミッド・ストラクチャ」で組み立てるのが基本だ。この構造によって話が不必要に長くならず、説得力が高まる。結論を出すためには、手元にある根拠を並べて「だから何?」と自問自答するのが効果的だ。
ロジカルであるとは、「意味がつながっている」ことを指す。結論と根拠が聞き手にとって論理的に接続しているかは、「~だから、~だ」と声に出して読んでみればチェックできる。日本人は結論を曖昧にしがちだが、不安でも明確に「結論」を主張することが重要だ。
聞き手を途中で迷子にさせないために、言葉もスライドも「スッキリ、簡単」に保つことが鉄則だ。専門用語やカタカナ語は避け、「中学生でも理解できるレベルの言葉」を選ぶ。スライドに文字が多いと、相手は資料を読むのに集中してしまい、話を聞かなくなる。視覚的に「読まずにすっと」理解できるかが重要だ。自分の努力や笑いといった不要な情報も削る。ビジネスの場でのプレゼンは、まずはロジックを中心に組み立てることが大事だ。
右脳に働きかける感情技術
ロジックだけでは人は動かない。正しいことを言っても、聞き手の感情を揺さぶり、頭の中にイメージを想像させなければ意味がないのだ。
具体的なイメージを抱かせる方法として、まず図や画像、動画などの「ビジュアル」を見せるのが最もシンプルで効果的だ。ビジュアルがない場合は、「例えば」と具体的な事例を示すことで、聞き手のイメージを具体的にする。さらに「想像してみてください」「あなたがもしこの世界を経験するとしたらどうでしょう」と問いかけることで、聞き手が自らイメージの中に入り込み、想像を膨らませてくれる。
しかし、左脳で理解させ、右脳にイメージを想像させても、「いい提案だね」と言われるだけで終わることがある。人は聞いた話をすべて覚えているわけではないからだ。そこで重要になるのが、自分の伝えたいことを一言のキーワードで表す「超一言(ちょうひとこと)」だ。覚えやすく、プレゼン全体を表現するようなキャッチーな言葉が理想的だ。
著者はソフトバンクアカデミアでの体験を通じて、この「超一言」の威力を実感している。Eコマースの納期管理戦略を「キチリクルン」という親しみやすいネーミングで表現したプレゼンが、孫正義氏の印象に強く残ったのだ。どんなに優れた内容でも、覚えやすいキーワードがなければ相手の記憶に残らない。
実践で活かす技術と心構え
この本では、話を組み立てるための代表的なフレームワークをいくつか紹介している。
- PREP法 (Point-Reason-Example-Point):結論→理由→具体例→結論の順で、論理的説明と具体例を組み合わせるのに適している。
- SDS法 (Summary-Detail-Summary):要点→詳細→要点の順で、短いプレゼンで簡潔に伝えたい場合に活用される。
- PCSF法 (Problem-Change-Solution-Future):問題→変化→解決策→未来の順で、新規事業や革新的な取り組みの提案に適している。
これらのフレームワークを状況に応じて使い分けることで、効果的なプレゼンが可能になる。
プレゼン中は、自分を客観的に見る「メタ認知」を心がけ、聞き手側から自分がどう見えているかを意識する。実践的な方法として、実際に聞き手の席に座ってそこからの見え方を確認したり、自身のプレゼンを録画して客観的にチェックしたりする練習が有効だ。
著者が何百人ものプレゼンを指導して気づいたのは、「声が小さい」という単純な問題だった。聞き手に伝わらない原因の7割は、これだけだという。ただし、単純に声を張り上げても伝わらない。力んで声を出すより、「届ける」という意識が大切だ。
声のトーンを変化させることも重要だ。プレゼン冒頭で「みなさん今日は」と言うとき、どんな思いを込めているのかを自覚する。言葉に意味合いを込めることで自然とトーンが変わり、聞き取りやすい声になる。
どのようなスキルやテクニックがあっても、最終的には伝える側の「想い」と「情熱」が相手を動かす。自分が一番詳しく、自信を持ち、好きなコンテンツを「自分の存在をかける」くらいの気持ちで語るからこそ、人は行動に移る。プレゼンはライブコンサートに似ており、話し手も自分のメッセージに合わせて「演じる」意識が重要だ。
実践では、突然意見を求められた場合、まず落ち着いて質問の意図(Yes/Noか、アイデアか、懸念点か)を把握し、その後「結論+3つの根拠+具体例」のピラミッド構造で答える練習をすると良い。意見を否定しがちな上司には、あえて「ツッコミどころ」を用意する応用テクニックも紹介されている。
プレゼン力は才能ではなく、練習で伸ばせるスキルだ。多くのビジネスパーソンはプレゼンの練習をしないが、ミュージシャンや俳優のように、繰り返し練習し、録音して聞き直し、フィードバックを受けることが効果的だ。「配慮はしても、遠慮はするな」。自分の意見を明確に伝えることが重要なのである。
感想
この本を読んで最も印象的だったのは、「動かしてなんぼ」という著者の一貫した主張だ。これまでプレゼンとは、高校や大学のゼミでやってきたような、調べたことを整理して発表するものだと考えていた。しかし、ビジネスでのプレゼンは根本的に違う。相手に行動を起こしてもらうためのツールなのだ。
この違いは手法の問題ではなく、哲学の違いといえる。高校の授業発表や大学のゼミでは「調べたことを正確に伝える」ことが評価される。先生や同級生に「よく調べましたね」と言われることがゴールだった。しかし、ビジネスでは「相手を動かす」ことが唯一の目的になる。どんなに緻密な調査や豊富な知識があっても、相手に具体的な行動を促せなければ失敗なのだ。
著者が指摘する「声が小さい」「情報の詰め込み過ぎ」といった問題は、多くの人がゼミ発表のスタイルから抜け出せないことが原因かもしれない。学校では「網羅的に調べること」「論理的に完璧であること」が求められたが、ビジネスでは「簡潔に要点を伝えて相手を動かすこと」が重要になる。この切り替えができないまま社会人になってしまうのだろう。
日常の会話でも、この考え方は応用できそうだ。友達に映画を勧める時も、ダラダラとあらすじを説明するより「絶対面白いから見て。理由は3つあって…」と構造化した方が相手は動いてくれるはずだ。
この本は、プレゼンのテクニック集ではない。「伝える」から「動かす」への発想転換を教えてくれる一冊だった。この考え方の変化は、現代のコミュニケーション全般に通じる重要な視点と感じた。
- Audible聴き放題対象作品: 【Audibleの無料体験で聴く】